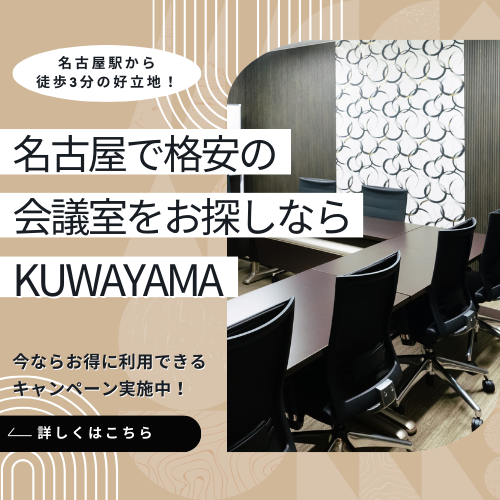目次
 会議をスムーズに進行させるうえで欠かせない存在が「タイムキーパー」です。
会議をスムーズに進行させるうえで欠かせない存在が「タイムキーパー」です。
時間の管理が不十分な会議は、話が脱線して目的を見失ったり、重要な議題に十分な時間を割けなかったりと、生産性が著しく低下します。
特にビジネスシーンでは、限られた時間の中で意思決定を行い、次のアクションへつなげることが求められます。
そのため、タイムキーパーのやり方を理解し、適切に実践することが会議の成功を左右すると言っても過言ではありません。
本記事では、「会議 タイム キーパー やり方」というキーワードで検索する方に向けて、タイムキーパーの役割や準備方法、実際の進め方、そして評価されるためのコツまでを詳しく解説します。
これから初めてタイムキーパーを担当する方はもちろん、すでに経験がある方でも「より効果的な時間管理術」を身につけたい場合に役立つ内容です。
タイムキーパーの役割と重要性
タイムキーパーとは何をする役割か
タイムキーパーとは、会議の進行時間を管理し、全体の時間配分を守るためにサポートする役割を担う人のことです。
ファシリテーター(司会進行役)とは異なり、主に裏方として「今どのくらい時間が経過しているか」「次の議題に進むべきか」などを把握し、必要に応じて参加者や進行役に時間を知らせます。
具体的には、以下のような業務を行います。
-
会議の開始・終了時刻の確認
-
各議題ごとの持ち時間の管理
-
進行が遅れている場合のアラート
-
残り時間や終了予定の告知
-
延長・短縮が必要な場合の判断サポート
タイムキーパーは、ただ時計を見るだけではなく、会議全体の流れを把握しながら、最適なタイミングで進行に介入する判断力が求められます。
時間通りに終わることはもちろん、議論の質を維持しつつ全員が納得できる結論にたどり着くよう調整するのが、タイムキーパーの本来の役割です。
タイムマネジメントができていないと起こる問題
会議の目的を達成できない
時間配分を意識せずに会議を進めると、どうしても前半の議題に時間を使いすぎ、重要な項目を十分に議論できないまま終了してしまうことがあります。
その結果、「決定事項が曖昧なまま終わる」「結論を持ち越す」といった事態が発生し、会議そのものの目的を達成できなくなります。
タイムキーパーがいない会議ほど、このような“時間切れによる未決定”が起こりやすいのです。
参加者の集中力が低下する
ダラダラと長引く会議は、参加者の集中力を奪います。
特に、予定時刻を過ぎても終わらない場合や、話が何度も同じところを循環する場合は、心理的な疲労感が蓄積し、生産的な意見が出にくくなります。
タイムキーパーが適切に時間を区切り、進行にメリハリをつけることで、参加者の集中力を維持する効果が期待できます。
時間延長で他の業務に影響が出る
会議の延長は、単に時間を浪費するだけではありません。
その後に予定されている他の会議や業務、商談などに影響を及ぼす可能性があります。
特に多忙な職場では、1つの会議が遅れるだけでスケジュール全体が崩れることもあります。
タイムキーパーがしっかり時間管理を行えば、こうした“連鎖的な遅延”を防ぎ、組織全体の生産性向上にも貢献できます。
タイムキーパーの基本的なやり方
事前準備とタイムスケジュールの作成
会議の目的と議題の確認
 タイムキーパーの仕事は、会議が始まる前から始まっています。
タイムキーパーの仕事は、会議が始まる前から始まっています。
まず重要なのは、会議の目的と議題を明確に把握することです。
目的によって、時間配分の基準や進行スピードは変わります。
たとえば、「決定会議」では議論よりも結論を重視し、「報告会」では各担当者の発表時間が鍵となります。
議題の優先順位を整理し、どの議題にどれだけの時間をかけるかを事前に理解しておきましょう。
時間配分の計画立案
次に、会議の全体時間をもとに細かなタイムスケジュールを作成します。
たとえば、60分の会議であれば以下のように構成できます。
-
開会・目的説明:5分
-
議題1:20分
-
議題2:20分
-
議題3:10分
-
まとめ・次回確認:5分
このように「どこに何分使うか」を可視化しておくことで、進行役も安心して会議を運営できます。
また、発言が長くなりがちな人や議題には、あらかじめ短めの時間を設定するなど、リスクを織り込んだ計画が効果的です。
時間計測と告知の方法
効果的な時間の告知タイミング
会議中の時間告知は、ただ残り時間を伝えるだけではなく、進行のリズムを作る重要な要素です。
一般的には、「残り5分前」「終了1分前」「予定時刻になったタイミング」の3段階で伝えるのが効果的です。
また、議題の切り替え時に「次の議題に移ります」と明確にアナウンスすることで、会議全体のテンポが良くなります。
告知する際のコツと注意点
時間告知は、冷静かつ簡潔に伝えることがポイントです。
「あと5分しかありません!」と焦らせる言い方ではなく、「残り5分ですので、まとめに入りましょう」といった建設的な言い方を心がけましょう。
また、告知のタイミングをミスすると議論が中断される可能性があるため、発言の区切りを見計らって伝える配慮も重要です。
時間調整のテクニック
計画より早く進んでいる場合の対応
予定より早く進行している場合は、無理に時間を埋める必要はありません。
むしろ、その余裕を「質の高い議論」や「次回への確認」に活用しましょう。
たとえば、「今のうちに課題整理をしておきましょう」と提案すると、会議の完成度が上がります。
時間が押している場合の軌道修正
反対に時間が押している場合は、すぐにファシリテーターへ伝達し、優先順位の再調整を促すことが重要です。
「この議題は次回に持ち越す」「決定部分だけ先に確認する」など、進行役と協力して柔軟に対応しましょう。
タイムキーパーが冷静に状況を分析し、軌道修正できるかどうかが、会議成功の分かれ道となります。
タイムキーパーを成功させるポイント
ファシリテーターとの連携方法
 会議においてタイムキーパーが最も重視すべきは、ファシリテーター(進行役)との連携です。
会議においてタイムキーパーが最も重視すべきは、ファシリテーター(進行役)との連携です。
タイムキーパーがいくら正確に時間を測っていても、ファシリテーターがその情報をうまく活用できなければ意味がありません。
まず会議前に、以下のような項目をファシリテーターと共有しておきましょう。
-
各議題の予定時間と優先順位
-
時間が押した際の対応方針(短縮・省略・次回持ち越しなど)
-
タイムキーパーが声をかけるタイミングや方法
このように事前に打ち合わせをしておくことで、会議中もスムーズに意思疎通ができます。
また、ファシリテーターが議論に夢中で時間を忘れているときには、メモやジェスチャーで静かに伝えるなど、相手のペースを崩さないサポートを意識しましょう。
タイムキーパーは進行役の「右腕」として、会議全体を裏から支える存在なのです。
参加者への事前共有の重要性
タイムキーパーが機能するためには、参加者全員が時間管理の重要性を理解していることが前提となります。
会議前に、議題ごとの持ち時間や終了時刻を資料やアジェンダに明記し、「時間厳守で進行する」旨を伝えておきましょう。
これにより、発言者が自ら発言時間を意識するようになり、タイムキーパーが頻繁に注意を促す必要もなくなります。
また、初めてタイムキーパーを設ける場合は、「本日は時間通りに進行するため、タイムキーパーを設定しています」と冒頭で説明しておくと、会議全体が協力的な雰囲気になります。
このように全員が“時間を共有する意識”を持つことで、会議の進行スピードと質が飛躍的に向上します。
終わりと始まりの時間管理
タイムキーパーに求められるのは「会議中の管理」だけではありません。
開始と終了の時間を守ることも極めて重要です。
予定より遅れてスタートすると、全体のタイムスケジュールが崩れる原因になります。
また、終了時間を過ぎてしまうと参加者の予定に影響が出るだけでなく、会議そのものの印象も悪化します。
タイムキーパーは、開始5分前には参加者の着席を促したり、終了10分前にはまとめに入るよう合図を出したりと、終わりを意識した進行を心がけましょう。
特に「あと5分です」と声をかけた後に議論が続く場合は、「では残り1分で結論を出しましょう」と締めに向けた促しを行うと効果的です。
会議の始まりと終わりをきっちり管理することで、全体が引き締まり、参加者に“時間を大切にする会議”という印象を与えられます。
ツールの活用方法
タイマーやスマホの使い方
現代のタイムキーパーは、ストップウォッチやスマートフォンのアプリを活用するのが一般的です。
たとえば、スマホの「時計」アプリにはカウントダウン機能やアラーム機能が備わっており、議題ごとに設定しておくことで自動的に時間を知らせてくれます。
また、アプリによっては「残り時間を視覚的に表示」するタイプもあり、参加者に画面を見せることで自然に時間意識を促せます。
特に複数の議題がある会議では、タイマーを段階的に設定しておくと便利です。たとえば、
-
議題1:20分 → アラーム音「ピッ」
-
残り5分:軽い通知音
-
終了:明確なベル音
といったように、音の違いで段階的に知らせるとスムーズです。
ただし、通知音が大きすぎると会議を中断してしまうため、音量やタイミングには注意が必要です。
システムを使った管理方法
オンライン会議や大規模ミーティングでは、専用の時間管理ツールやシステムを導入するのも効果的です。
たとえば「Google Meet」や「Zoom」などでは、画面上にタイマーを共有できるアドオンや拡張機能があります。
これを利用すれば、全員がリアルタイムで残り時間を確認でき、タイムキーパーが逐一声をかける手間を減らせます。
また、議事録作成ツールやプロジェクト管理アプリ(例:Notion、Asanaなど)と連携することで、議題ごとの所要時間を記録・分析することも可能です。
これにより、「どの議題に時間を使いすぎたか」「次回はどのくらい配分すべきか」といった改善にもつなげられます。
つまり、ツールを活用することで、タイムキーパーの作業効率と精度を同時に高めることができるのです。
タイムキーパーの注意点と評価を上げるコツ
よくある失敗と対策
時間を見過ごしてしまう場合の対処法
 会議中、議論が白熱してつい時間を見逃してしまうことは誰にでもあります。
会議中、議論が白熱してつい時間を見逃してしまうことは誰にでもあります。
そうならないためには、“二重のチェック体制”を構築しておくことが大切です。
たとえば、スマホのタイマーと手元の時計を併用したり、進行表に経過時間をメモしたりするなど、複数の方法で確認できるようにしておきましょう。
また、途中で時間が押してしまった場合は、「現在予定より5分押しています」と冷静に共有することが大切です。
時間の遅れを正確に報告することで、進行役や参加者が判断しやすくなります。
焦って慌てるよりも、冷静で正確な報告が信頼を得るポイントです。
単なる時間告知で終わらないために
タイムキーパーは、ただ「時間です」と伝えるだけの役割ではありません。
会議全体を見渡し、「どの議題を優先すべきか」「今どの段階にいるのか」を理解したうえで、進行を支援する必要があります。
たとえば、「残り5分です。結論をまとめましょう」や「次回の確認だけ先に行いましょう」といったように、次のアクションを促す言葉を添えると、非常に印象が良くなります。
この一言によって、会議が締まり、参加者全員が目的意識を持って終われるのです。
高評価を得るための工夫
役割発言後のフォローアップ
タイムキーパーが「残り5分です」と告知した後、会議がどう動いたかを観察し、必要であれば軽くフォローすることも大切です。
たとえば、議論が止まらない場合には「では、最後に確認事項だけお願いします」と声を添えたり、終了後に「今回の時間配分はこのように推移しました」と共有したりするなど、時間の使われ方を可視化すると評価が上がります。
「タイムキーパーがいることで、会議の質が上がった」と思われることが、信頼につながるのです。
議論の質を高める介入方法
タイムキーパーが議論に直接参加することは少ないものの、必要な場面では上手に介入することも求められます。
たとえば、発言が偏っている場合に「他の方の意見も伺ってからまとめましょう」と提案したり、議題から逸れている場合に「この話題は次回の議題に移してもよいでしょうか」と促したりすると、議論の流れが整います。
こうした介入は、単に時間を守るためだけでなく、会議全体の質を高める“進行支援”として高く評価されるポイントです。
まとめ
タイムキーパーは、単なる「時計係」ではなく、会議の成功を裏で支える重要なポジションです。
時間を管理しながら、進行役や参加者の動きを見守り、適切なタイミングで情報を伝えることで、会議全体をスムーズに導きます。
この記事で紹介したように、
-
会議の目的と時間配分を明確にする
-
ファシリテーターと連携する
-
残り時間を適切に告知する
-
状況に応じて柔軟に時間調整する
といったポイントを押さえることで、誰でも効果的にタイムキーパーを務められます。
最後に覚えておきたいのは、「時間管理は信頼管理」であるということです。
会議を時間通りに進められる人は、職場でも信頼を得やすく、組織全体の効率向上にも貢献できます。
ぜひ本記事の内容を参考に、次の会議で「理想のタイムキーパー」として活躍してください。







![[8A]](https://kuwayama-kaigishitsu.com/wp-content/uploads/2021/12/pho_016-scaled.jpg)
![[408]レガート](https://kuwayama-kaigishitsu.com/wp-content/uploads/2021/12/pho_034-scaled.jpg)
![[404]ラルゴ](https://kuwayama-kaigishitsu.com/wp-content/uploads/2021/12/fe2643f92b17f220f81a735db9f7c0ed.png)
![[407]モデラート](https://kuwayama-kaigishitsu.com/wp-content/uploads/2021/12/c879aece10831303602d1d7ec53ac48c.png)
![1月現在[予約受付期間]](https://kuwayama-kaigishitsu.com/wp-content/uploads/2021/12/335_SYP00289-scaled.jpg)