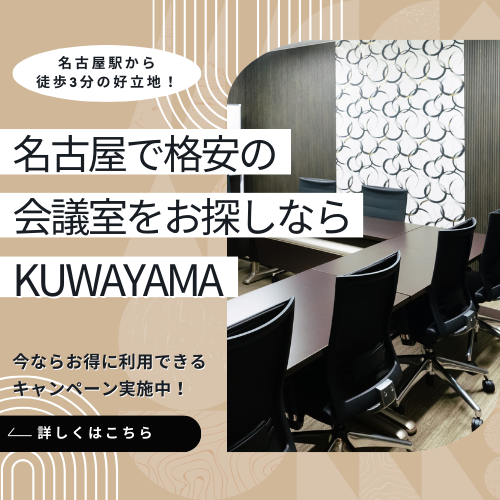目次
 近年、就職活動のスタイルが大きく変化する中で、企業にとって「会社説明会」の在り方も再考が求められています。
近年、就職活動のスタイルが大きく変化する中で、企業にとって「会社説明会」の在り方も再考が求められています。
従来のようにスライドを用いた一方的な情報提供では、就活生の関心を引きつけることが難しくなってきています。
多くの学生は、インターネットやSNSを通じて簡単に企業情報を手に入れられるようになっており、説明会に参加する際には「そこにしかない価値」や「実際に体験しないとわからない魅力」を求めるようになっているのです。
こうした背景から、企業は自社の魅力をいかに“ユニークに”伝えるかが勝負となってきています。
面白く、インパクトのある説明会は、それだけで話題になり、参加者の記憶に残りやすくなります。
さらに、学生自身がその場で感じた楽しさや学びをSNSでシェアすることで、自然と企業の認知拡大にもつながるのです。
本記事では、まず就活生が会社説明会に何を求めているのかを整理し、次に学生の印象に残る「面白い会社説明会」の特徴を解説します。
そして実際に高い評価を得ているユニークな説明会の事例を9つ紹介し、それらの成功の共通点を読み解いていきます。
さらに、自社でも再現可能な“面白くてユニークな説明会”の作り方について、ステップごとに詳しくご説明します。
就活生が会社説明会に求めるもの
実際の仕事内容や職場の雰囲気が分かること
就活生にとって、最も関心が高いのは「実際にどんな仕事をするのか」「職場の空気は自分に合っているか」といったリアルな情報です。
企業のホームページや採用パンフレットには載っていない、現場の雰囲気や一日の業務の流れを知ることで、企業選びの判断材料になります。
そのため、実務担当者の1日に密着した動画の上映や、実際のプロジェクトを模擬体験するワークなどは高評価を得やすいコンテンツです。
単なるスライド説明ではなく、体験を通じて「この仕事が面白そう」「この職場で働きたい」と思わせる工夫が求められます。
会社の独自性や強みを理解できること
就活生は、多くの企業説明会に参加する中で、似たような説明に飽きてしまうことがあります。
その中で印象に残るのは、やはりその企業ならではの「独自性」や「強み」が明確に伝わる説明会です。
たとえば、「自社の製品が世の中でどう役立っているか」を実例を交えて話したり、ユニークな社風や文化を体験できるコンテンツを用意したりすることで、企業の魅力がより深く、具体的に伝わります。
先輩社員の生の声を聞けること
 説明会で先輩社員が登壇し、就活当時の思いや入社後のリアルな体験を語ってくれると、学生は大きな安心感を得られます。
説明会で先輩社員が登壇し、就活当時の思いや入社後のリアルな体験を語ってくれると、学生は大きな安心感を得られます。
「自分もこんな風に活躍できるかもしれない」と将来の姿をイメージできるからです。
座談会やQ&Aセッションを通じて、学生が直接質問できる機会を設けることも大切です。
実際に働いている人の本音が聞ける場は、企業に対する信頼感を高める有力なコンテンツです。
面白い会社説明会の特徴
学生が主体的に参加できる双方向型のプログラム
一方通行の説明会では学生の集中力が続かず、印象にも残りません。
そのため、双方向でコミュニケーションを取りながら進行するスタイルが注目されています。
例えば、グループワークやディスカッションを組み込んだ形式では、学生自身が考え、発言し、他者と意見交換をすることが求められるため、能動的な姿勢が引き出されます。
また、フィードバックをその場で行うことで、学びと気づきがより深まります。
ゲームや体験型コンテンツなどの楽しめる要素
学生が「楽しかった!」と感じる会社説明会は、自然と記憶にも残りやすく、好印象につながります。
最近では、謎解きゲームやロールプレイングを取り入れた体験型の説明会が人気を集めています。
たとえば、自社の業務内容をゲーム形式で理解してもらうプログラムや、チームで課題に挑戦するワークなど、遊びの中に学びがある設計が有効です。
楽しさと学びを両立できる説明会は、学生の満足度も高く、SNSなどでの拡散も期待できます。
他社にはない独自のコンセプトやストーリー性
ユニークな会社説明会は、「コンセプトの明確さ」と「物語性」がカギです。
「テーマパークのような会社説明会」「未来の自分を発見できる冒険型説明会」など、企業の特徴を反映したストーリーを設計することで、参加者の没入感が高まります。
こうした演出により、「この企業の考え方は面白い」「他とは違う視点を持っている」といった印象を強く残すことができます。
ブランド戦略の一環として、説明会自体が企業の価値を伝えるツールになるのです。
ユニークな会社説明会の事例9選
1. 絶対に本音で話さざるを得ない会社説明会
「就活生に“本音”を伝えたい」と企画されたこの説明会では、企業側も参加学生も匿名でトークを展開。
会社の“良い面”だけでなく、“大変な部分”や“失敗談”も包み隠さず共有するスタイルが話題となりました。
参加者には仮名の名札が渡され、自由に発言できる環境を演出。
人事担当と現場社員がざっくばらんに語る本音トークが、学生から「信頼できる会社」と好評を得ています。
2. みんなが知らないたまごの世界~八千代ポートリーが食卓に届けたいものとは
八千代ポートリーでは、「たまご」の流通過程や食の安全について、クイズ形式で学べる説明会を開催。
参加者は“ひよこからたまごが食卓に届くまで”を追体験しながら、業務内容や企業理念を学びます。
食品業界に興味がある学生だけでなく、「面白そう」と口コミで広がり、幅広い層の学生を惹きつけました。
説明会後のアンケートでも、理解度・満足度ともに非常に高評価です。
3. 採用担当直伝!就活準備セミナー&イオンリテール研究
イオンリテールが開催したのは、「採用の裏側がわかる説明会」。
自社の説明にとどまらず、業界研究やES・面接のコツまでレクチャーする“就活セミナー”と組み合わせたハイブリッド企画です。
学生の視点に立ったコンテンツ構成により、「選考前の不安が減った」「他の企業の説明会より役立った」との声が多く、ブランド価値向上にもつながっています。
4. 体験型ゲームで学ぶ、ITインフラ・運用の今と未来
IT企業が実施したこの説明会では、インフラ運用の仕事を「脱出ゲーム形式」で体験できます。
学生たちは仮想システムに発生するトラブルをグループで解決しながら、インフラ業務の魅力を学んでいきます。
参加者からは「難しい仕事かと思っていたが、面白くて興味が湧いた」と好評で、技術系学生のエントリー増加につながった事例です。
5. 人材のプロと一風変わった就活準備!MBTI自己分析×座談会!
自己分析をエンタメ化したこの説明会では、MBTI診断(性格類型分析)を使って、自分の特性や向いている仕事を見つけるワークを実施。
診断結果をもとに、社員との座談会で「そのタイプに向いている業務」などを深掘りする内容で、学生の満足度は非常に高くなっています。
「自分らしい就活のヒントになった」とSNSでも拡散され、多数の応募を呼び込みました。
6. 面接官の評価方法、公開します。
 面接が苦手な学生にとって、面接官が何を見ているのかは非常に気になるポイント。
面接が苦手な学生にとって、面接官が何を見ているのかは非常に気になるポイント。
この会社では、実際の評価基準や過去の面接例を赤裸々に紹介し、参加者に模擬面接も体験してもらう説明会を開催しました。
採用の裏側に触れることで企業に対する信頼感が高まり、「選考に進みたい」と思わせる動機づけにもつながっています。
7. 謎解き型企業研究ワーク ~日立ソリューションズを解き明かす!~
日立ソリューションズが企画した説明会は、参加者が“謎解き”を通じて企業理解を深めていく構成。
例えば、「このプロジェクトの成功要因は何か?」といったクイズにグループで挑戦しながら、会社の強みや仕事の進め方を学んでいきます。
遊びながら学べる設計により、堅い印象のある企業でも「親しみやすい」と好評を博しました。
8. 企業理解!謎解きゲーム型体感ワーク
類似の体験型ワークとして、ゲーム会社が開催した「謎解きゲームで企業理解を深める」説明会も注目されています。
ストーリー仕立てで展開される中で、企業理念や職種の特徴、求める人材像が自然に理解できるよう設計されており、「楽しく企業理解できる」「ストレスがなくて良い」と、学生から高い評価を受けています。
9. 広告業界を楽しく学べる超実践型脱出プログラム
広告業界に興味がある学生向けに行われたこの説明会では、“広告制作現場から脱出せよ!”という設定で、チームごとに企画・コピー・プレゼンを通じて課題解決に挑戦。ゲーム性と業務理解を融合させたこのプログラムは、「実際の仕事に近い体験ができた」として、広告業界志望者の注目を集めました。
面白い会社説明会の作り方
ステップ1|ターゲット学生を明確にする
まず最初に行うべきは、「誰に向けた説明会なのか」を明確にすることです。
自社が求める人物像やスキルセットに応じて、対象となる学生の学年、専攻、志向性を絞り込みましょう。
論理的思考力が求められる職種であれば理系学生や情報系専攻が中心となる一方、柔軟な発想力や対人スキルが重視される職種では文系やクリエイティブ志向の学生にフォーカスするべきです。
対象が明確になることで、コンテンツ設計や説明のトーンも的確になり、結果として学生とのミスマッチを減らすことができます。
さらに、SNSや求人媒体などのプロモーション方法もターゲットに合わせて最適化すれば、集客の質も高まり、説明会自体の効果が向上します。
ステップ2|説明会のコンセプトを決める
 次に大切なのが、「コンセプト設計」です。
次に大切なのが、「コンセプト設計」です。
単に自社を紹介する場ではなく、学生に何を感じてほしいのか、何を持ち帰ってもらいたいのかを明確にし、それを軸に説明会を組み立てていきます。
「体験を通じて業務理解を深める」「“働く”を楽しく伝える」「他社との違いを明確に伝える」といったテーマを設定することで、ブレのない構成が可能になります。
また、参加者の印象に残りやすいタイトルやキャッチコピー(例:「脱出型企業説明会」「就活×謎解きゲーム」など)を工夫することも、ユニークさを演出するポイントです。
ステップ3|学生が楽しめるコンテンツを用意する
① 体験型ワークを取り入れる
業務内容を“体感”できるワークは、理解を深めるだけでなく、楽しさ・リアルさを演出する強力な武器です。
たとえば、営業職であれば模擬商談、開発職であれば簡易的なプロダクト設計体験など、業務の一部を疑似体験できる仕掛けを作るとよいでしょう。
② 先輩社員との座談会を充実させる
 学生が最も信頼する情報源の一つが「先輩社員の生の声」です。
学生が最も信頼する情報源の一つが「先輩社員の生の声」です。
リアルなキャリア体験や社風について自由に質問できる座談会の時間は、企業理解を深める絶好の機会です。
可能であれば、若手・中堅・ベテランの社員それぞれを登壇させ、さまざまな立場からの話を聞ける構成にすると、学生の共感が得やすくなります。
③ ゲームやエンタメ要素を組み込む
説明会にゲーム性やエンタメ要素を取り入れることで、参加者の集中力とエンゲージメントを高めることができます。
クイズ形式の企業紹介、チーム対抗型のワーク、ストーリーベースの謎解きなど、遊びながら学べる仕組みは学生の記憶に残りやすく、口コミによる拡散も期待できます。
ステップ4|説明会の進行を工夫する
① 退屈させない進行スケジュール
長時間にわたる説明会でも、進行にメリハリがあれば学生の集中は保たれます。
話す→体験する→休憩→話す→ワーク、といったように、聴講・体験・交流の要素をバランスよく組み合わせることで、飽きさせない構成にしましょう。
また、時間配分やセッションごとの目的を明確に伝えることで、学生にとっての“得られる価値”がはっきりし、納得感をもって参加できます。
② 双方向コミュニケーションができる要素を取り入れる
ZoomやTeamsを活用したオンライン説明会でも、チャットやブレイクアウトルーム機能を使って双方向性を担保することが可能です。
質問タイムやリアルタイムアンケートなど、学生が自分の意見や疑問を自由に表現できる仕掛けを設けることで、受動的な説明会から能動的な“対話の場”へと進化します。
オフラインの場合も、アイスブレイクや軽いワークを取り入れて緊張をほぐし、会話のしやすい雰囲気づくりを心がけましょう。
ステップ5|フォローアップ施策を実施する
説明会が終わった後も、学生との関係性を継続することが非常に重要です。フォローアップとしては、以下のような施策が有効です。
-
参加御礼メール+次のステップ案内(選考やイベントへの誘導)
-
アンケートを活用したニーズ分析と個別対応
-
説明会で紹介した資料・動画のアーカイブ配信
-
社員からのフォローメールやSNSでの発信
学生に「この企業は本気で向き合ってくれている」と感じさせる対応は、エントリーや志望度向上に直結します。
説明会での印象を継続・深化させる仕組みを用意することで、採用活動全体の質を高めることができます。
まとめ
ユニークな会社説明会は、単なる“変わり種”ではありません。
学生にとって魅力的かつ意味のある体験を提供することで、企業理解を深め、志望度を高める重要な手段となります。
就活生が求めているのは、リアルな情報・楽しさ・そして自分との接点です。
事例に見るような創意工夫を凝らした説明会を参考に、自社にしかできないコンテンツを企画し、参加者の心をつかみましょう。
名古屋駅周辺で会社説明会をお探しなら貸し会議室KUWAYAMA
就職活動のピーク時期には、名古屋駅周辺で会社説明会を開催したいと考える企業が数多くあります。
特に東海エリアの学生にとってアクセスが良く、主要な鉄道各線が集中する名古屋駅は、集客の観点でも非常に有利な立地です。
そのため、会社説明会や採用イベントの会場選びは、ただスペースを確保するだけでなく、「学生が来やすく、印象に残る場であること」が大切になってきます。
その中でもおすすめの会場が、名古屋駅から徒歩圏内にある【貸し会議室KUWAYAMA】です。
会社説明会に適したさまざまな広さの会議室が用意されており、少人数制のセミナーから100人規模の合同説明会まで柔軟に対応可能です。
会場は清潔感があり、明るく開放的な空間であるため、企業イメージを損なうことなく、学生にも好印象を与えることができます。
ぜひ一度ご検討くださいませ。
皆様からのご予約をお待ちしております!








![[8A]](https://kuwayama-kaigishitsu.com/wp-content/uploads/2021/12/pho_016-scaled.jpg)
![[408]レガート](https://kuwayama-kaigishitsu.com/wp-content/uploads/2021/12/pho_034-scaled.jpg)
![[404]ラルゴ](https://kuwayama-kaigishitsu.com/wp-content/uploads/2021/12/fe2643f92b17f220f81a735db9f7c0ed.png)
![[407]モデラート](https://kuwayama-kaigishitsu.com/wp-content/uploads/2021/12/c879aece10831303602d1d7ec53ac48c.png)
![1月現在[予約受付期間]](https://kuwayama-kaigishitsu.com/wp-content/uploads/2021/12/335_SYP00289-scaled.jpg)