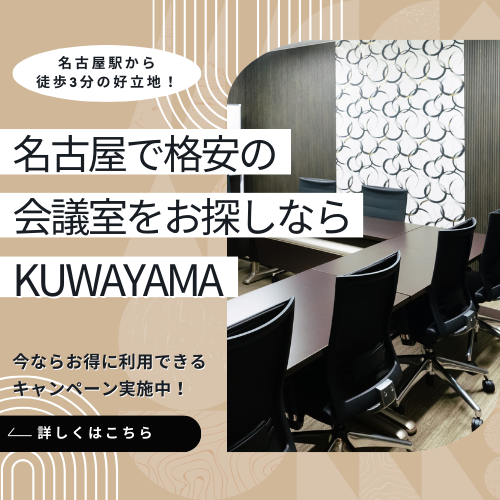目次
 会社説明会は、企業と参加者が最初に直接触れ合う重要な場です。
会社説明会は、企業と参加者が最初に直接触れ合う重要な場です。
その中でも「挨拶」は、説明会全体の雰囲気を決定づける大切な要素です。
特に会社側が行う挨拶は、参加者の第一印象に直結し、企業理解やエンゲージメントにも影響を与えます。
就職活動中の学生や転職希望者は、挨拶の言葉や態度から「この会社は自分に合っているか」「信頼できる企業か」といった判断を下すため、軽視できません。
本記事では、会社説明会における挨拶の基本構成や実践テクニック、目的別の挨拶例、さらにはオンライン開催時の工夫や事前準備チェックリストまで、会社側が成功するためのノウハウを完全ガイドとして解説します。
会社説明会における挨拶の重要性と基本構成
第一印象を決める冒頭挨拶の役割
会社説明会において冒頭の挨拶は、参加者が企業に抱く第一印象を決定づけます。
短時間であっても、明るい表情、誠実な態度、そして自信のある声で伝えることにより、参加者に「安心感」と「期待感」を与えられます。
逆に、曖昧な表現や冗長な話し方は集中力を削ぎ、説明会全体への意欲を低下させてしまいます。
冒頭挨拶は「これから有意義な時間になる」というメッセージを伝える役割を果たすため、入念な準備が欠かせません。
挨拶で伝えるべき3つの要素
企業理念とビジョンの簡潔な表現
挨拶の中で必ず触れておきたいのが、企業理念やビジョンです。
ただし、長々と説明する必要はなく、端的にまとめて「自社がどんな未来を描いているのか」を伝えることがポイントです。
学生や求職者は、自分の価値観と企業の方向性が合致しているかを判断する材料とするため、共感を得やすい言葉選びが求められます。
参加者への感謝と歓迎の気持ち
会社説明会に足を運んでくれた参加者に対して「数ある企業の中から当社を選んでいただきありがとうございます」と感謝を述べることは不可欠です。
歓迎の姿勢を明確に示すことで、参加者は心理的に安心し、積極的に説明会に臨めるようになります。
特に就活生や転職希望者は緊張していることが多いため、冒頭で感謝と歓迎を伝えることが信頼関係構築の第一歩となります。
説明会の流れと期待値の設定
挨拶では「本日は会社概要のご紹介、先輩社員の体験談、質疑応答の流れで進めてまいります」といった形で説明会の全体像を提示することも重要です。
事前に流れを伝えることで参加者は安心し、集中力を持って臨むことができます。
また、「最後に質疑応答の時間を設けていますので、ぜひ積極的にご質問ください」と期待値を設定することで、双方向的な参加姿勢を促すことが可能です。
適切な挨拶時間の目安と配分
 挨拶は短すぎても長すぎても効果が半減します。
挨拶は短すぎても長すぎても効果が半減します。
一般的には 3〜5分程度 が適切な時間配分です。
その中で「自己紹介・感謝の言葉」に1分、「企業理念とビジョン」に1〜2分、「説明会の流れの提示」に1〜2分を充てるとバランスが取れます。
コンパクトかつ要点を押さえた挨拶が、参加者の集中力を維持する鍵です。
印象に残る挨拶の実践テクニック
簡潔で分かりやすい言葉選び
会社説明会における挨拶は、参加者の理解度や集中力を大きく左右するため、言葉選びが非常に重要です。
企業側が意識すべきは「簡潔さ」と「分かりやすさ」です。
特に就活生や転職希望者は、まだ業界知識が十分ではない場合も多く、専門的な用語や社内独自の言い回しを多用してしまうと、説明が伝わりにくくなり、企業への理解が深まらないまま終わってしまいます。
挨拶では、できる限り日常的に使われる言葉を選び、「誰が聞いてもわかる説明」を心がけましょう。
例えば「BtoBのシナジー効果」といった表現ではなく「企業同士が協力して互いに利益を生み出す仕組み」と言い換えるなど、少し工夫するだけで理解度が大きく変わります。
また、簡潔な言葉選びは「誠実さ」や「信頼感」を参加者に与えるため、会社側の姿勢を伝える上でも効果的です。
専門用語を避けた平易な表現
会社説明会の挨拶では、できるだけ専門用語を避けることが重要です。
学生や求職者にとって馴染みのない単語を多用すると「難しそうな会社」「自分には合わないのでは」といった心理的な壁を作ってしまう危険があります。
たとえば「ROE」や「EBITDA」といった財務用語をそのまま出すのではなく、「利益率」や「企業の稼ぐ力」と言い換えるとスムーズに理解してもらえます。
挨拶は企業の第一印象を左右するため、あえて専門性を強調するよりも、わかりやすさを優先するほうが効果的です。
具体的な数字やエピソードの活用
 抽象的な表現は曖昧に受け取られてしまうことが多いため、具体的な数字やエピソードを交えて話すと説得力が格段に増します。
抽象的な表現は曖昧に受け取られてしまうことが多いため、具体的な数字やエピソードを交えて話すと説得力が格段に増します。
例えば「当社は安定した成長を続けています」というよりも「直近5年間で売上が毎年10%ずつ成長しています」と伝えるほうが、参加者に企業の実績を明確にイメージさせられます。
また、社員の体験談や成功事例を挨拶の中に盛り込むことで、参加者は「ここで働く自分」をよりリアルに想像できます。
数字は客観的な信頼性を、エピソードは感情的な共感を引き出すため、両方をバランスよく取り入れることが印象に残る挨拶のコツです。
声のトーンと話すスピードの調整
どれほど良い内容を用意していても、声のトーンや話すスピードが適切でなければ、参加者に正しく伝わりません。
特に会社説明会の挨拶では、落ち着いたトーンと明瞭な発声を意識することが求められます。
声の高さはやや明るめに、ボリュームは会場の後方まで届く程度を目安にすると効果的です。
話すスピードは、普段の会話よりもややゆっくりを意識することで、参加者に安心感を与え、内容を理解しやすくなります。
また、強調したい部分では少し間を置くことで、言葉に重みを加えられます。
会社側の挨拶は「信頼できる企業かどうか」を見極められる場でもあるため、声の使い方一つで参加者の印象は大きく変わるのです。
アイコンタクトとボディランゲージ
挨拶の内容だけでなく、視線や身体の動きといった非言語的な要素も参加者の印象に大きく影響します。
会場の一部だけを見続けるのではなく、左右や前後に視線を巡らせながらアイコンタクトをとることで、参加者一人ひとりに「自分に語りかけてくれている」という感覚を持たせることができます。
また、ボディランゲージも大切で、軽く手を添えて強調したり、背筋を伸ばした姿勢を保ったりすることで、信頼感と自信を表現できます。
逆に、腕を組む、下を向く、動きが大きすぎるといった仕草は、威圧感や不安を与えてしまうため注意が必要です。
企業側の挨拶は、言葉以上に「態度」が伝わる場であることを忘れないようにしましょう。
参加者の緊張を和らげる工夫
多くの学生や求職者は会社説明会という場に緊張感を抱いています。
その緊張を和らげる工夫を挨拶に盛り込むことは、円滑な説明会運営に直結します。
例えば「本日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます」といった感謝の言葉に加えて「今日はリラックスしてお話を聞いていただければ幸いです」と声をかけるだけで、参加者は安心できます。
また、季節や天候に触れた一言や、自社のちょっとしたユーモアを交えた紹介を盛り込むと、会場が和みやすくなります。
さらに、軽いアイスブレイクを挨拶の中に取り入れることで、参加者の表情が柔らかくなり、その後のプログラムへの参加意欲も高まります。
会社側の挨拶は「緊張を和らげる雰囲気づくり」も担っていると認識すると、より効果的な場作りが可能になります。
説明会の目的別挨拶パターン
新卒採用説明会での挨拶例
新卒採用向けの会社説明会では、学生の多くが初めて社会人と接する場となるため、挨拶は特に慎重に行う必要があります。
学生にとって会社側の挨拶は「社会人の姿勢」そのものを映す鏡であり、誠実さや信頼感を伝えられるかどうかが大きな分かれ目となります。
挨拶の冒頭では「数ある企業の中から当社の説明会にご参加いただきありがとうございます」と感謝を示し、続けて「皆さんが社会人として一歩を踏み出す大切な時期に、私たちの会社を知っていただけることを嬉しく思います」と歓迎の気持ちを伝えると効果的です。
また、新卒採用説明会は学生が「社会人になる不安」を抱えているため、その心理に寄り添った言葉を挟むことで安心感を与えられます。
学生の不安を解消する言葉かけ
学生は「社会に出てやっていけるだろうか」「自分に合う会社を見つけられるだろうか」といった不安を抱えて説明会に参加しています。
そこで会社側の挨拶では「皆さんも不安や疑問を持っていると思いますが、今日の説明会を通じて少しでも安心していただければ嬉しいです」といった言葉を添えると、参加者は安心して耳を傾けてくれます。
学生にとって挨拶が「共感」につながることで、企業への信頼感が高まり、その後の説明もスムーズに伝わります。
成長機会のアピール方法
 新卒学生にとって最大の関心事は「自分がどのように成長できるか」です。
新卒学生にとって最大の関心事は「自分がどのように成長できるか」です。
会社側の挨拶では「当社は新入社員研修やOJT制度を整え、皆さんが一歩ずつ成長できる環境を用意しています」と具体的に伝えると効果的です。
抽象的な「成長できます」という表現よりも「入社後3年間で先輩社員がマンツーマンで指導します」といった具体的な制度や実績を挙げることで、学生は未来をイメージしやすくなります。
挨拶で「安心して成長できる場」であることを示すと、その後の会社説明全体への期待感も高まります。
中途採用説明会での挨拶例
中途採用向けの会社説明会は、すでに社会人経験を持つ参加者が対象となるため、挨拶の内容も新卒採用とは大きく異なります。
中途採用希望者は「自分のキャリアを活かせるか」「次の会社でどのような成長ができるか」に注目しているため、挨拶ではその点を押さえたメッセージが必要です。
冒頭で「これまでのご経験を当社でぜひ活かしていただきたい」と伝えることで、参加者は自分のキャリアが歓迎されていると感じます。
また、キャリア形成やスキルアップにつながる情報を交えると、信頼と期待を持ってもらえます。
キャリアビジョンへの訴求
中途採用説明会では「会社に入った後、どのようなキャリアを描けるか」が最も重視されます。
そのため、挨拶では「当社では経験を持つ方に新しいチャレンジの場を提供し、マネジメントや専門領域のスキルをさらに伸ばせる環境を整えています」と伝えると効果的です。
個人の成長が会社の成長と結びついていることを強調すると、参加者は「ここでなら自分のキャリアをさらに発展させられる」と感じやすくなります。
即戦力への期待表現
中途採用者に対しては「即戦力としての期待」を明確に伝えることも重要です。
例えば「皆さまのこれまでの経験やスキルをすぐに活かしていただき、チームに新しい視点をもたらしていただけることを期待しています」といった表現を用いると、参加者は「求められている」と実感し、自信を持って説明会に臨むことができます。
会社側の挨拶に即戦力としての期待を盛り込むことは、中途採用希望者のモチベーションを高める効果があります。
インターンシップ説明会での挨拶例
インターンシップ説明会の挨拶は、新卒採用説明会や中途採用説明会とは異なるアプローチが必要です。
インターン参加者は「実際の業務を体験してみたい」「社会人の雰囲気を知りたい」という目的を持っているため、挨拶では「体験を通して得られる学び」や「挑戦の場としての魅力」を強調することが大切です。
例えば「今日の説明会を通して、インターンシップでどのような経験ができるのかを知っていただければと思います」と伝えると、参加者は安心して内容を受け止められます。
また、インターンを通じたキャリア形成のきっかけづくりを意識した言葉を盛り込むと効果的です。
効果的な説明会運営と挨拶の連携
プログラム全体を見据えた挨拶設計
会社説明会での挨拶は、単なる冒頭の儀礼的な一言ではなく、プログラム全体の流れをスムーズに進めるための「導入部分」として大きな役割を持っています。
会社側は、説明会全体をひとつのストーリーとして捉え、その第一章を担うのが挨拶であると意識すると効果的です。
例えば、冒頭の挨拶で「本日は、当社の理念・事業内容、そして皆さんのキャリアに直結する成長機会についてご紹介します」と伝えると、参加者は自然にプログラム全体に集中できるようになります。
挨拶をプログラム全体の設計と連動させることで、参加者は途中で迷わず内容を理解でき、最後まで高い関心を持ち続けることができます。
つまり、挨拶は「会社説明会全体のナビゲーション」として機能するのです。
質疑応答への自然な誘導
会社説明会では、説明が一方通行になりすぎると参加者の理解が浅くなり、納得感を持てないまま終わってしまうことがあります。
そこで重要なのが「挨拶の段階で質疑応答へ自然に誘導しておくこと」です。
例えば「本日の説明を聞いて疑問点や関心を持った点があれば、ぜひ最後の質疑応答で遠慮なくお聞かせください」と冒頭で伝えておくと、参加者は安心して質問の準備ができます。
締めの挨拶でも「皆さまからの質問が、私たちにとっても新しい気づきになります」と一言添えると、双方向性が強調され、より活発なやり取りにつながります。
会社側が質疑応答を歓迎する姿勢を挨拶で示すことは、企業文化の開放性や柔軟性をアピールするうえでも効果的です。
双方向コミュニケーションの促進
会社説明会を「一方的に会社が情報を伝える場」と捉えるのではなく、「参加者と会社が対話をする場」と位置づけることで、参加者の満足度は大きく高まります。
そのためには挨拶の中で「今日は皆さんとの対話を大切にしたいと思っています」といったメッセージを発信することが効果的です。
特に若い世代は受け身の説明よりも、参加体験型の説明を好む傾向があるため、挨拶の中でコミュニケーションの重要性を強調すると良いでしょう。
アイスブレイクの導入タイミング
参加者が緊張しているまま説明会を進めてしまうと、質問も出にくくなり、会場全体が硬い雰囲気になってしまいます。
そのため、冒頭の挨拶に軽いアイスブレイクを取り入れるのがおすすめです。
たとえば「今日の会場に来るまでに雨に降られた方はいらっしゃいますか?」といった簡単な問いかけや、会社にまつわるちょっとしたクイズを交えることで、場の雰囲気が和みます。
挨拶の一部として自然に取り入れることで、参加者との距離を縮めやすくなります。
参加者の反応を見ながらの調整
挨拶は一方的に原稿を読むのではなく、参加者の表情や反応を観察しながら柔軟に調整することが大切です。
もし会場全体が緊張しているようであれば、軽いジョークを加えて空気を和ませる、逆にざわついているようなら声のトーンを落ち着かせて注目を集めるなど、臨機応変な対応が求められます。
挨拶で参加者の心理状態を把握できれば、その後の進行もよりスムーズに行えます。会社側が参加者の空気を読んで調整する姿勢は「柔軟な企業風土」の象徴にもなります。
フォローアップにつながる締めの挨拶
説明会の最後に行う締めの挨拶は、単なる終わりの言葉ではなく、参加者との「今後のつながり」を意識して設計することが重要です。
例えば「本日の説明会をきっかけに、少しでも当社の雰囲気を感じていただけたら嬉しいです。
さらに詳しい情報はWebサイトや資料でご覧いただけますし、後日ご質問をいただければ担当者が丁寧に対応いたします」と伝えることで、説明会終了後のフォローアップに自然につなげられます。
また「今日ここにいる皆さんと、将来一緒に働ける日を楽しみにしています」といった前向きなメッセージを添えると、参加者のモチベーションが高まり、好印象を持ったまま帰ってもらえるでしょう。
会社側の締めの挨拶は、説明会全体の印象を決定づける大切な要素であるため、入念に準備する必要があります。
オンライン説明会での挨拶の工夫
カメラ目線と表情の重要性
オンライン説明会では、対面と異なり参加者と直接目を合わせることができません。
そのため、カメラを通じて「目を見て話している」ように感じさせる工夫が必要です。
画面下や別の資料を見ながら話してしまうと、参加者からは「視線が合わない」「自分に語りかけられていない」といった印象を持たれてしまいます。
挨拶の際には、特にカメラ目線を意識し、落ち着いた笑顔で話すことで、参加者は親しみやすさや信頼感を抱きやすくなります。
また、表情が乏しいと画面越しでは冷たく感じられがちなので、やや大きめのリアクションを意識することも効果的です。
頷きや微笑みを交えながら挨拶することで、「オンラインでも温かい雰囲気をつくることができる会社」という印象を与えられます。
音声品質とネットワーク環境の確認
どれほど内容のある挨拶をしても、音声が途切れたり雑音が混ざったりすると、参加者にストレスを与え、集中力を損ないます。
特に説明会の冒頭での挨拶は、会社の第一印象を決める大切な場面ですから、クリアな音声環境の確保が不可欠です。
事前に外付けマイクやヘッドセットを用意し、リハーサルを通じて音量や音質を確認しておくと安心です。
また、ネットワーク環境が不安定だと映像や音声が途切れる可能性があるため、有線接続を利用したり予備の回線を準備したりすることが推奨されます。
挨拶の中で「万が一通信トラブルが発生した場合には、すぐに再接続を試みますのでご安心ください」と一言添えると、参加者に対して丁寧で信頼できる印象を与えることができます。
画面共有を活用した視覚的演出
オンライン説明会の特徴は、スライドや資料を画面共有で簡単に提示できる点です。
挨拶の段階からビジュアル要素を取り入れることで、参加者の注意を引きつけやすくなります。
例えば、会社のロゴやミッションステートメントをシンプルにまとめたスライドを冒頭で表示すれば、言葉だけでは伝わりにくい企業の雰囲気や理念を効果的に印象づけられます。
また、挨拶の流れに沿って「本日のプログラム」「担当者紹介」といったスライドを活用すると、参加者が全体像を把握しやすくなり安心感を持って説明会に臨めます。
視覚的な情報を取り入れることで、オンライン特有の単調さを解消し、記憶にも残りやすい挨拶が可能になります。
チャット機能を使った参加者との交流
 オンライン説明会では、参加者との距離が物理的に離れているため、対面以上に一方通行になりやすいという課題があります。
オンライン説明会では、参加者との距離が物理的に離れているため、対面以上に一方通行になりやすいという課題があります。
そこで効果的なのがチャット機能を活用した交流です。挨拶の際に「ぜひ気軽にチャットにコメントしてください」と促すことで、参加者は受け身ではなく主体的に参加しやすくなります。
例えば、冒頭で「音声や画面は問題なく見えていますか?」と問いかけ、チャットで反応をもらうことで、早い段階から双方向のコミュニケーションを築けます。
さらに、簡単な自己紹介や意見を募ると、参加者の緊張を和らげ、説明会全体の雰囲気を柔らかくする効果があります。
オンライン挨拶にチャットを組み合わせることは、参加者との距離を縮める有効な方法です。
リアクション機能の活用方法
近年のオンライン会議ツールには「拍手」や「いいね」などのリアクション機能が搭載されています。
挨拶の中で「よければ拍手ボタンで反応してください」と呼びかけると、参加者が簡単に意思表示でき、場の一体感が生まれます。
特に対面での拍手や頷きが得られないオンラインでは、こうした機能を積極的に活用することで、参加者の存在を感じながら進行できるメリットがあります。
挨拶の最後に「ここから一緒に進めていきましょう」と前向きに促し、リアクションを引き出すと、参加者のモチベーションを高める効果も期待できます。
技術トラブル時の対応例
オンラインならではのリスクとして避けられないのが、音声・映像の乱れや画面共有の不具合といった技術トラブルです。
挨拶の中で「もし私の声や映像が途切れてしまった場合は、チャットでお知らせください」と一言添えるだけで、参加者は安心して説明会に臨めます。
また、実際にトラブルが起きた際には、慌てず「一時的に接続が不安定になっております。
すぐに復旧しますので少々お待ちください」と冷静に伝えることが大切です。
こうした対応の仕方自体が、会社の柔軟性や誠実さを示す場面となるため、事前に対応マニュアルを準備しておくとさらに安心です。
挨拶の事前準備とチェックリスト
挨拶原稿の作成と練習方法
会社説明会での挨拶は即興で対応できそうに思えますが、実際には準備の有無が印象を大きく左右します。
特に会社側の挨拶は、参加者が最初に触れる企業の「顔」とも言える部分であり、事前の原稿作成と練習が不可欠です。
原稿を作成する際は、長々とした文章を書くのではなく「キーメッセージ」を中心に構成することがポイントです。
冒頭の挨拶、企業紹介、参加者へのメッセージ、説明会の流れ、といった大きな流れを箇条書きで整理しておくと、当日スムーズに話せます。
さらに、練習の際には声に出して読むだけでなく、録音や録画を行って自分の話し方を客観的に確認することが効果的です。
声のトーン、話すスピード、言葉の癖などを改善することで、本番では自信を持って臨むことができます。
キーメッセージの明確化
挨拶の中で必ず伝えたい内容は何かを明確にしておくことが、説得力あるスピーチの第一歩です。
例えば「企業の理念」「成長の方向性」「参加者への期待」の3点を柱に据えると、話の焦点がぶれず、聞き手にも強い印象を残せます。
メッセージが多すぎると逆に伝わらなくなるため、シンプルに絞り込むことが重要です。
時間配分のリハーサル
挨拶は長すぎても短すぎても印象を損ないます。
一般的には3~5分程度が目安ですが、会社説明会の規模やプログラムによって調整が必要です。
リハーサルを行い、実際に話してみて「どこで時間が伸びてしまうか」「どこを簡潔にできるか」を確認しておくと、当日の進行に余裕が生まれます。
当日の身だしなみと会場設営
挨拶の言葉だけでなく、視覚的な印象も会社説明会の雰囲気を大きく左右します。
話し手自身の身だしなみはもちろん、会場の雰囲気づくりにも注意を払う必要があります。
身だしなみに関しては、清潔感のあるスーツや控えめなアクセサリー、整えられた髪型など、誠実さを感じさせる装いが基本です。
また、会場設営においては、参加者が入室した瞬間から「この会社は整っている」と感じてもらえるように、椅子の配置や資料の配布状況、マイクやプロジェクターの動作確認を徹底しましょう。
挨拶は単なる言葉のやり取りではなく、空間全体を通して会社の姿勢を示す場です。そのため、物理的な準備と話す側の外見を整えることは、参加者に安心感を与えるうえで欠かせない要素です。
想定外の状況への対応準備
説明会当日は、どれほど準備をしていても予期せぬ出来事が起こる可能性があります。
例えば、開始時刻に参加者が遅れて集まる、機材トラブルが発生する、想定以上の質問が飛び交う、といったケースです。
こうした状況で慌てずに対応できるかどうかが、挨拶の印象に直結します。
事前に「万が一の場合の対応フレーズ」を用意しておくと安心です。
例えば「お待ちいただきありがとうございます。それでは、準備が整いましたので開始いたします」といった切り替えの言葉を持っておけば、想定外の出来事もスムーズに収めることができます。
また、挨拶の中に柔軟さを持たせることも重要で、事前の準備を踏まえながらも状況に合わせて言葉をアレンジできる余裕があると、参加者から「落ち着いた会社」「信頼できる担当者」と見てもらえるでしょう。
まとめ
 会社説明会における挨拶は、単なる形式的な一言ではなく、会社側が参加者に与える第一印象を決定づける非常に重要な要素です。
会社説明会における挨拶は、単なる形式的な一言ではなく、会社側が参加者に与える第一印象を決定づける非常に重要な要素です。
挨拶の内容、声のトーン、表情、アイコンタクト、さらにはオンラインならではの演出まで、すべてが参加者の印象形成に影響します。
会社側は、挨拶を単なる開会の挨拶として終わらせるのではなく、説明会全体の流れや目的、参加者とのコミュニケーション設計に組み込むことで、より印象深く、理解しやすい説明会を提供できます。
会社説明会での挨拶は「会社の顔」としての役割を持つ重要な場面です。
事前準備を怠らず、参加者の立場に立った配慮ある挨拶を心がけることで、会社の魅力を最大限に伝え、採用活動の成果向上にもつなげることができます。
会社側としての挨拶の質が高まれば、参加者の満足度や信頼感が向上し、結果として優秀な人材の獲得にも大きく貢献するでしょう。







![[8A]](https://kuwayama-kaigishitsu.com/wp-content/uploads/2021/12/pho_016-scaled.jpg)
![[408]レガート](https://kuwayama-kaigishitsu.com/wp-content/uploads/2021/12/pho_034-scaled.jpg)
![[404]ラルゴ](https://kuwayama-kaigishitsu.com/wp-content/uploads/2021/12/fe2643f92b17f220f81a735db9f7c0ed.png)
![[407]モデラート](https://kuwayama-kaigishitsu.com/wp-content/uploads/2021/12/c879aece10831303602d1d7ec53ac48c.png)
![1月現在[予約受付期間]](https://kuwayama-kaigishitsu.com/wp-content/uploads/2021/12/335_SYP00289-scaled.jpg)